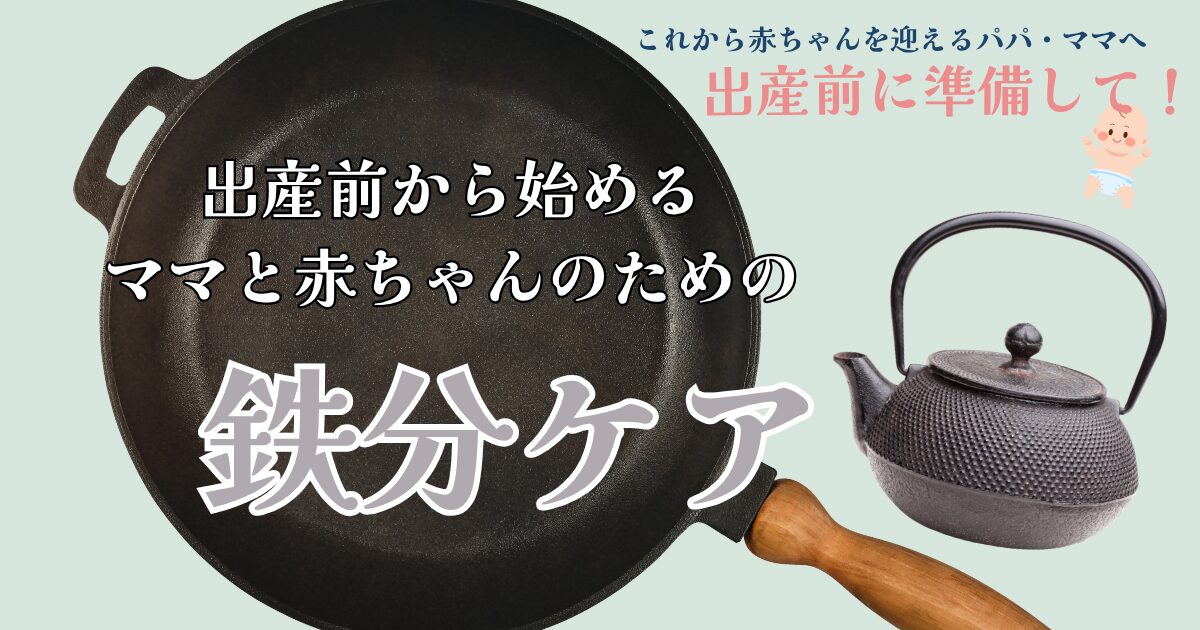初めての子育てで「子育てに車は必要?」と悩むパパママは多いのではないでしょうか。ベビーカーでの移動や買い物、通院など、車があると便利な場面は多くあります。この記事では、車のある暮らしとない暮らしの違いや、車を持つべき理由をわかりやすく解説します。

いろいろ比較すると悩んでしまう!そんな方は 星香の結論! をご覧ください。
子育てに車は必要かどうかを考える前に
まずは、車がある生活とない生活の違いを知っておきましょう。どちらにもメリットとデメリットがあり、家族のライフスタイルや居住環境によって最適な選択は異なります。
車があると安心できるシーン
赤ちゃん連れの外出は、荷物が多く移動の負担が大きくなります。車があれば、天気に左右されず、体調が悪いときや夜間の通院にもすぐ対応できます。また、子どもが成長してからも、習い事やお出かけなどで活躍します。
車がなくても困らないケース
都市部に住んでいて交通アクセスが良い場合は、車を持たなくても十分に暮らせる場合があります。カーシェアリングやタクシーアプリを活用すれば、維持費を抑えつつ必要なときだけ車を使うことも可能です。
子育て世帯が車を持つメリットとデメリット
実際に車を所有した場合の利点と注意点を整理してみましょう。
メリット:移動が楽になり家族の行動範囲が広がる
買い物や保育園の送迎など、日々の生活が格段に快適になります。急な雨や体調不良のときも、子どもを安全に連れて移動できる点は大きな安心材料です。
デメリット:維持費が高く駐車スペースの確保が必要
ガソリン代や保険、車検などのコストは年間で数十万円かかることもあります。特に都市部では駐車場代も負担になるため、費用面での検討は欠かせません。
子育てに車が必要な家庭の特徴
では、どんな家庭にとって「車があると助かる」と言えるのでしょうか。
郊外や地方に住んでいる家庭
公共交通が少ないエリアでは、車は生活の必需品です。保育園や病院、スーパーが徒歩圏内にない場合、車があることで日常の移動がスムーズになります。
双子や年の近いきょうだいがいる家庭
荷物が多く移動が大変な時期には、車があることでお出かけのハードルが下がります。特に雨の日や真夏の外出では大きな助けになります。
車を持たない場合の代替手段
車を持たずに快適に子育てをする方法も増えています。
カーシェアリングを上手に活用する
最近では、月会費無料で使えるカーシェアもあり、必要なときだけ車を利用できます。子どもの通院や週末の買い物に使うだけでも十分便利です。
配送サービスをフル活用する
重い荷物を運ぶ必要がないよう、ネットスーパーやベビー用品の定期配送を取り入れると負担が減ります。車がなくても快適な育児環境を整えられます。
星香の結論! 子育てするには車がないとダメな5つの理由
理由1:1か月健診から、すでに車がないとキツい!
最初に「車、必要だな」と思うのは、退院のタイミング……と思いきや、実はそうでもありません。退院は夫や家族が迎えに来てくれればなんとかなります。
本当に困るのは 1か月健診(+必要なら2週間健診)。私の場合は退院時の赤ちゃんの体重が順調に増えていなかったので、2週間後に来るように言われました。
- ベビーカーは産後1か月くらいから
- 新生児はフニャフニャで軽く、ベビーカーに乗せるのも不安
- 抱っこ紐は使えても両手が空くわけではない
- おむつ・着替えなど荷物がとにかく多い
- 産後1か月のママの体調はまだまだ万全ではない
徒歩・電車で行くには負担が大きすぎます。
出産前に車を用意しておき、産院への道も一度確認しておくと安心です。
理由2:意外と知らない!産後の通院回数、実はとんでもなく多い!
1か月健診が終わってもすぐに訪れるのが「予防接種ラッシュ」。
1歳までのスケジュールはこんなにびっしりです。
0か月(出生後)
B型肝炎(1回目)
2か月ごろ
ヒブ(1回目)
小児用肺炎球菌(1回目)
四種混合(1回目)※ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ
B型肝炎(2回目)
ロタウイルス(1回目)※経口・病院によって2回 or 3回
3か月ごろ
ヒブ(2回目)
小児用肺炎球菌(2回目)
四種混合(2回目)
ロタウイルス(2回目)
※ロタウイルスはワクチンの種類によって「2回完了」「3回目あり」に分かれます。
4か月ごろ
ヒブ(3回目)
小児用肺炎球菌(3回目)
四種混合(3回目)
(必要なら)ロタウイルス(3回目)
5〜7か月
B型肝炎(3回目)※ここで完了
6か月ごろ
BCG(1回)※結核の予防
9か月ごろ(任意接種)
インフルエンザ(1回目・2回目)※毎年流行前に
1歳になったら(追加で大事!)
MR(麻しん・風しん)1回目
水ぼうそう(1回目)
おたふくかぜ(任意)
そして、予防接種は小学校入学前まで続きます。
……これだけの回数、赤ちゃんを抱えて徒歩・バスで通うなんて本当に大変。
予防接種がある限り、車は必須レベルです。
産まれたばかりの赤ちゃんを両手で抱っこし、通勤ラッシュの混雑した電車の優先席の前に、つり革も持たずに立っていたママを見たことがあります。そばに立っていたご婦人が席を譲るようにお願いしていましたが、もし変わってもらえずに急ブレーキでかかっていたら・・・・・本当に見ていられない状況でした。
理由3:保育園・幼稚園の荷物、想像以上!!
入園すると、毎日の持ち物がとにかく多い!
- お昼寝布団
- おむつ
- 着替え
- 使用済みのおむつ
- 水筒
- 上履き
- 工作で作ってきた巨大な「謎の作品」
週末には「とりあえず全部お持ち帰り」なんてことも。
さらに、上の子の送迎と下の子の抱っこが重なるともう限界。
徒歩や公共交通は現実的ではありません。
理由4:親だって、子どもにいろんな経験をさせたくなる
1歳を過ぎて歩けるようになると、近所の公園だけでは物足りなくなるのは……実は子どもより親。
「もっと楽しめる場所に連れて行きたい」
「水族館・動物園・屋内遊び場に行ってあげたい」
「子連れOKのランチにも挑戦したい」
そう思うたびに車があると、行ける世界が一気に広がります。
子どものためにも、自分のためにも、行動範囲を広げるには車が必要です。
理由5:近年の猛暑は、車なしでは厳しすぎる
真夏にベビーカーで外出するのは危険なレベル。
「外に出たいけど暑すぎる」 → 結果、室内キッズスペースや涼しい施設に出かけることに。
でもそこはたいてい遠い……。
暑さ対策としても車は重要な“避難手段”になります。
まとめ:星香の結論
同じころに出産した私の友人は、「車の運転が怖いから」と、本当は一戸建てがよかったけど、駅近でショッピングモールも目の前にあるマンションを選びました。でも、子どもが二人になったら、ついにペーパードライバー教習に通い始めました。いくらショッピングモールが近くても、大きな横断歩道を越え、ショッピングモールの駐車場を突っ切らないといけない大型ショッピングモールは子供二人連れのママにはどんなに重労働なことか。
どれだけ環境が良くても、子育ては車がないと本当に大変。
買うなら、そして練習するなら “出産前” が絶対におすすめです。
出産を控えているママ・パパへ。
未来の自分を助けるために、車の準備をしておきましょう!